Member
-

K.Yさん
フジッコフーズインドネシア
2011年入社。
商品開発や製造部門を経て、2022年よりフジッコフーズインドネシア出向。現在は現地でさつま揚げやかまぼこなどの「すり身製品」と蒸し豆や煮豆などの「豆製品」を製造販売しながら、インドネシアにおける市場調査と商品開発を進めて新規事業展開を模索している。 -

F.Mさん
海外事業推進
2019年キャリア入社。
インドネシアでの業務経験を活かし、2021年からインドネシア市場での事業立ち上げに尽力。東南アジアの食品市場に広い知識を持ち、現地での製品展開を推進している。 -

N.Hさん
海外事業推進
2023年キャリア入社。
前職でのお惣菜の製品開発を担当し、フジッコフーズインドネシアで商品開発サポートに従事。新しい製品のアイデアを海外市場に適応させる役割を担っている。
Introduction
フジッコは、インドネシア市場をターゲットにした海外事業の展開を進めています。
インドネシアは2億8000万人を超える巨大な人口を持つ一方、日本食への関心が高まっている地域です。
フジッコの健康的な食品を、現地の食文化にどのように融合させていくのか、
そして日本の「美味しさ」をどのように広げていくのか。
今回は、この挑戦に関わる3名のメンバーが、プロジェクトの舞台裏と未来へのビジョンを語り合います。
Talk Theme 01
インドネシア市場への進出と最初の一歩

F.M:私がインドネシア事業に加わった際に、先ずは日本食レストランの店舗数の多さ、人気の高さに驚きました。インドネシアには、うどんや牛丼、寿司、ラーメン店など沢山の日本食レストランがあり、現地の方に大人気ですが、一方で肥満や糖尿病に悩まされている方も非常に多いのが現状です。フジッコ製品で、バランスの良い日本型の食生活を広め、インドネシアの方の健康な食生活に貢献したいと思っています。インドネシアでは、若い人を中心に日本文化への興味、日本食の嗜好は高まっており、フジッコとしては、現地の人々に「美味しさと健康」を届けられるチャンスがあると考えます。

N.H:前職でも東南アジア市場にお惣菜を輸出していましたが、フジッコのお惣菜はインドネシア市場で受け入れられると感じています。将来的に和惣菜を総称して「フジッコ」と認識してもらえるような日が来ることを目指し、私たちはそのための第一歩を踏み出しています。



Talk Theme 02
インドネシア市場で直面した課題と現地の適応

K.Y:インドネシア市場は、日本とはまったく異なる環境です。物流インフラが整っていないため、保存料を使わないフジッコの方針に合わせた商品を現地に届けるのは難しい部分があります。特に冷蔵物流が未成熟であり、賞味期限を延ばすためにどうすればよいか、現地に合わせた開発が必要だと感じています。日本では当たり前の保存方法も、インドネシアでは適用できない場合があるため、商品開発の段階で工夫を重ねています。

F.M:味の好みも日本とは異なります。インドネシア人は辛味のある強い味を好みますが、フジッコの和食の良さを残しつつ、現地の好みに合う食感や味付けを模索しています。例えば、現地の人々が好むクリスピーな食感やクリーミーさを取り入れた商品の開発も行っています。現地市場にフィットさせる一方で、フジッコのブランドとしての一貫性を保つことが重要です。

N.H:現地での調査を進める中で、日本では健康食品として評価されている納豆やめかぶが、インドネシアでは「腐っている」と誤解されることがあると知りました。こういった文化的な違いにも対応しながら、新しい形で日本の食品を現地に伝えていく必要があります。また、SNSが非常に活発な市場なので、見た目にも映える商品開発が重要です。視覚的なインパクトを与えられる商品が、現地では人気を集めやすいです。

Talk Theme 03
インドネシア市場での製品展開と現地スタッフとの連携

K.Y:インドネシアでの事業運営には、現地のパートナー企業との連携が大きな役割を果たしています。彼らは、日本企業や日本食への理解が深く、現地の市場ニーズにも精通しています。日本語が通じる環境でもあるため、会社の経営状況や運営方針についてスムーズに情報共有できています。但し、現地スタッフとのコミュニケーションでは、お祈りの時間などに配慮するなど、宗教や文化の違いを理解しつつ、規模の小ささを活かしてフランクに話せる環境を作ることで、チームワークを高めています。

F.M:パートナーとの関係は非常に良好で、彼らのサポートのおかげで、現地でパートナーが経営しているスーパーマーケットへの商品導入やレストランへの展開も進んでいます。フジッコフーズインドネシアの商品は、彼らの店舗での実販売を通じて、インドネシア市場のリアルな消費者の声を聞くことができます。そのフィードバックを基に、製品を改良し、将来はインドネシア全土への販路拡大を狙います。現地の消費者ニーズに寄り添った商品展開は、事業の成功に必要不可欠です。

N.H:商品開発の際には、現地の技術者と細かな点までしっかりコミュニケーションを取る必要があります。例えば、製品の製造工程に関する説明が不十分だと、誤解が生じやすくなります。技術的な指示を英語や現地語で伝える際には、詳細な手順を明確にし、確実に理解してもらうためにも丁寧な説明を心がけています。

Talk Theme 04
フジッコブランドの未来と成長への展望

K.Y:現地工場はまだテストプラントに近い状態ですが、将来的にはフジッコブランドを広げ、インドネシア市場で大規模な生産体制を整えることを目指しています。日本での成功事例をインドネシアでも再現し、現地でのフジッコの認知度を高めていくことが目標です。

F.M:インドネシアでは、肥満や糖尿病の低年齢化も大きな社会問題となっています。将来フジッコフーズインドネシア商品を現地の学校給食などに取り入れて貰い、食育活動を通じて、子供たちが栄養に配慮した健康な毎日を送ることができるような取り組みも実施していきたいと思っています。

N.H:フジッコで開発した商品をインドネシア市場で成功させ、そこから世界へと発信していきたいと考えています。特に日本では扱っていないカテゴリーである魚肉練り製品の新しいバリエーションを開発し、現地での実績を積み重ねることで、フジッコのブランドを広げていくことが私たちの大きな目標です。
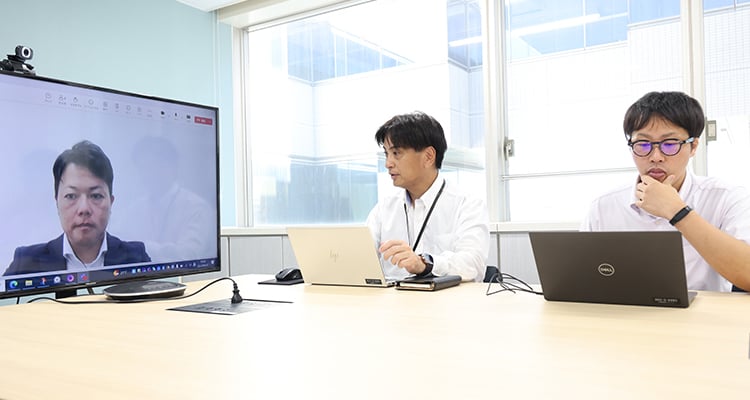





K.Y:フジッコがインドネシアに進出したきっかけは、現地の企業から「カスピ海ヨーグルトを一緒に展開したい」という声をいただいたことが始まりです。日本国内だけではなく海外の市場にも挑戦したいと思っていたときに、この提案を受けました。このプロジェクト自体はうまくいかなかったのですが、その後、現地の別の企業からお惣菜事業の提案をいただき、2019年にフジッコフーズインドネシアが誕生しました。